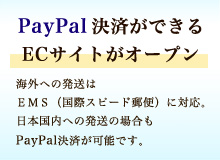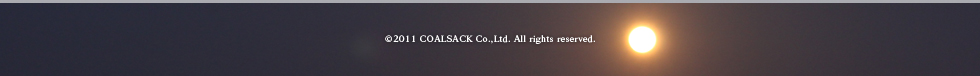1962年 身延山高等学校卒業。
1967年 立正大学文学部史学科卒業。
2004年 『石橋湛山-信念を背負った言説』(高文堂出版社)を刊行。本書は《日本図書館協会選定図書》となる。
2005年 11月8日 「平成17年度 身延山大学公開講演会」から講演を依頼され、「自由主義者 石橋湛山」を語る。
2007年 詩論集『雨新者の詩想』(コールサック社)より刊行。
僧侶になるべく仏教系の学校に学んでまもなく父が亡くなり、身延町波木井山円実寺にお世話になり、行学の二道に励む。毎日五時に起床するなど、躾は厳しかったが、住職夫妻の分け隔てない愛情に、育ての親の恩愛を知る。ふかい感謝が胸臆を離れない。
東京池上から千葉県鎌ヶ谷市、市川市、千葉市に転居し落ち着く。この間、水書房編集部や日蓮宗新聞社編集部に記者として勤める。
詩誌「光芒」同人。詩誌「COAL SACK」、その他にも寄稿。
千葉県詩人クラブ会員。立正大学国語国文学会会員。石橋湛山研究者。
【詩論の紹介】
朝倉宏哉詩集『乳粥』を味わう 石村柳三
―時間と空間の彼方へ眼を向ける詩想の聲
朝倉宏哉詩集『乳粥』が出版されて一ヶ月少々過ぎた十一月八日(水)、友人や詩 友による出版の祝いが、日本橋三井タワービル2F千疋屋フルーツパーラーメテール で午前十一時三十分から開かれた。二十名ほどの小じんまりとした楽しい出版記念会 であった。
このお祝いの席上での『乳粥』への評価は、私の思っていた通りの高いものであっ た。
なかでもこの詩人のあいさつを聞きながら、改めてリアルな眼と、ふかい思念と内在の感性から生まれた詩集であったことを知らされた。同時に謙遜と照れくさそうな 詩人の態度にも、やさしさのにじみでた感懐があった。
ところで『乳粥』の詩集の大きなモチーフというか、一つの要となっているテーマ は、詩人の背負っている認識(思念)にある、想念の抱く根源のさけび、人間としての聲にあったと私は思っている。
それは自らの自存してきた日常の生活や、それらを洞察し、これからの人生のあり ようとしての歩みに詩人の精神をみつめようとする。つまり自らの精神的内在をする 《旅》という彼方へ通底し、人間存在の聲を捉えようとしていることだ。
具体的にいえば、この詩集の主流をなす勝れた作品は愛する家族や肉親、息子の滞 在していたアジア (インド含んで)への親近と理解、そのあこがれのあった《旅の経験》から生まれ、この詩人の思索から生まれいずるべくして詩想された作品群と申 し上げてもいい。
表題作「乳粥」や「天池」「敦煌の町を歩く」また「この広い野原いっぱいの草」 「三本の樹」「ミイラと少女と二羽のスズメ」、もしくは「勝山号」「がんじがらめ」 「隠れびと」「微笑」などの力作が、詩人の詩心の絆から生まれたといえよう。就中、
「乳粥」「天池」「勝山号」は名詩編だと思っている。
ちなみに作品の構成は・章に八編、・章に八編、・章にも八編という、計二四編が収録されている。それに心情あふれる味わいのある〔あとがき〕。
この度の詩集に取り上げられた詩の作品は、今まで出版した五冊の詩集にあまり見られなかった《旅》を媒介しての時間(歴史)と空間に流れるアジアやインドの人びとのさけび、その風土に生きてきた人間性の沈黙、その精神をも汲み、その民族の情念の匂いを一行一行の作品に連ねていることだ。
たとえばその底流には、朝倉宏哉という詩人の脈搏と胸臆につちかわれていた時間的、空間的な歴史観への眼。それに重なる仏教、とくに原始仏教への関心もあり、この詩集の詩想を豊かに興味ふかいものにしていることがうかがわれる。
詩編「乳粥」について書かれた詩誌『COAL SACK』の小文によると、チベット仏 教に血脈する精神に興味をもち、その研究をしながら、これらの《旅》の詩編をつくっ たことが理解される。
むろん知識や知性だけですぐれた詩編は生まれるものではなく、それを凝視し、問う、詩人の思念のふかさがなければ、深化され、転化された佳編の詩は出来ないであ ろう。
それを問い、求める詩精神。もっと言い換えれば、そこに住み生きてきた人間の姿や、聲。地理的環境や風土のもつ聲を聴こうとしなければ、こうしたロマンとリアル の匂いする感情は表出できないかも知れない。
とまれ、「乳粥」にうたわれるラマ僧とそれを慕う難民の祈り。中国の侵略と弾圧によって、国をのがれ、異国で耐えながら生活するチベット難民。そうした人びとをささえていたのは、ダライ・ラマに帰依するチベット仏教の信仰心であり、その信仰に伝わる心の自由であろうと思われる。やすらぎの魂かも知れないのだが。
そういう人間のもつ純粋さを、この詩人は表白しているともいえよう。そうした詩語の詩行をランダムに引用してみよう。
〈五月のある朝、北インド・ダラムサラの山上の寺院にチベッ ト人たちが続続と集まってきた(略)ラマ僧たちの野太く澄 んだ声明が境内に流れヒマラヤの雪の連峰 へと渡っていく〉
〈この浄らかな静謐は何だろう(略)異国の旅人を引きつけるこの不思議な力〉
〈二千五百年前 ブッダ・ゴータマは苦行のあとの衰弱した 躰を村の少女スジャーターがささける乳粥で癒し 菩提樹の 下で瞑想した(略)わたしは仏教の誕生物語に想いを馳せ ……〉
そうした「乳粥」で癒されたゴータマは仏陀となり悟りを開くことになった。この悟りの境地のなかに、時間と空間の心音を感受し、視つめ、人間というものの存在、あるいは自存を問う詩人がいる。
そう生きている今を認識し、詩人朝倉宏哉は呼応し感応する。
〈悠久の今を共有しながら乳粥を味わうかれらの眼前にヒマラヤが聳え立つ その彼方は失われた祖国 今も喘いでいる 同胞がいる〉
「あなたもどうぞ」と信徒の一人が旅人の詩人に勧めた。旅人は器をもっていなかったが「お手を出しなさい」といった信徒の笑顔が菩薩のようにやさしかったという。 少年のラマ僧からの「乳粥」は詩人の手によそられ、見つめるこの「乳粥」はヒマラヤのようにまぶしかったというのだ。
とくに〈菩薩のように微笑んだ〉詩行の美しさ。さらに〈わたしはまぶしさを口に入れた 温かかった 質素だった 喉元を通るとき かすかにスジャーターの乳粥の味がした〉
何と質素で美しい光景であろう。その姿はヒマラヤの美しさに劣らぬ光景にあろうか。 終行の言葉は、 詩人がその 「乳粥」 の味をゴータマに献げた「少女スジャーターの味」だと表現する。
ロマンと、その人間性のもつ美学の詩といってもいい。
そこには仏教徒として生きている難民たちの人間的で、大切な呼応の生きかたのあり ようと風土の厳しい音色が流れ、伝わっているように共感される。
ではもう一編私にとって語っておきたい作品は、「天池」。
天山山脈のふところの天池のほとりに立ち
七色のさざなみを眺めていたとき
ふと湧いてきた想念があった
……人類が流した涙がここに溜まっている
この〈人類が流した涙が〉の一行が、本詩集の詩人の想念の言葉だろう。私はあつくなるものを感じながら、やはりこの詩行を味読し想念する。
時間と空間に消えつつ、消しえぬ歴史と風土の聲。そうした空間の時間は自由自在に捉えられ、詩人の詩想としてアジアとインドが美しく放散されている。その文化文明の歴史の悲劇の涙を共感させつつ。
こうした詩人の心情のさけびの聲が、ありふれた思念としてではなく、現実をひく眼と歴史の認識の感性をもって詩語詩想されていることだ。特色の一つといっていい。
朝倉宏哉という詩人の「今、立っている」境地がここに知られるものがある。そしてそれは大切なことでもある。
ともあれ、こうした作品は誰にでも書けるものではない。人間を見つめ、歴史を見つめ、自然を見つめ、それらに語りかけ自問転化する、内在の力から生まれるものであるのかも知れないと私は考えている。
詩集『乳粥』の詩人は、大学時代に「史学」を専攻し学んだというが、その眼が心情の底にあり流れていたと思われる。
またもう一つ、私はここで是非語っておきたい詩編がある。「明日から来る今日」 の作品だ。鳴海英吉という詩人の三回忌の《墓参り》をモチーフにしたものだが、その詩行にある
明日から来る
今日がある
その今日を
生きていけば楽しい
藤代聡麿
この言葉が印象に残った。
ここには「時間」と「空間」が、過去↓現在↓未来へだけ移るものではなく、今日は明日から、明日は昨日からという現在・過去・未来が自由自在に捉えられる思惟(認識)が暗示され、その眼にある大事さを教えられる。
時間もしくは歴史観、空間に自在に巡る思惟の眼。そこに洞察する現存の眼。時間を固定して捉えるのではなく、自在観の思念の時間として問うことも、「生きる」ことには必要であろう。
こうした考え方は余談ではあるが、道元の大著『正法眼蔵』に説かれる「時間論」にある。道元の「時間論」としても知られている。
詩人にとっては、こういう詩想の「時間論」の把握や感性も重要であり、背負う大切さでもあろう。
そのような意味というか、立場から、私はユニークな「明日から来る今日」の詩を評価している。
さて紙幅のこともあり、最後にこの詩人の『乳粥』に対峙し、矜持していた姿勢というか、態度について一言申し上げておきたい。
「二十一世紀初頭に生存する地球一市民として、何を拠り所に生きていけばよいのか」(あとがき)と。
そこには詩人の自問自答する「思念」のさけびがあろう。そのような詩人として、人間としての姿勢がある。とおとい姿勢論として。
少なくとも、そうした個としての自覚があればこそ、この第六詩集があり、詩人としての詩想の聲を放っているといえようか。
もう一つ感受し、忘れてはならないのはこの詩人の来歴から述べられた「年輪と体験という五感」の大事をだ。この「年輪から流露する体験という感性」にこそ、求道的詩心を見つめる朝倉宏哉という詩人がアンテナを張り、立っていたのだ。詩人の凝視であり、思索思念年輪の歩みとして、力強さと美学をともなった詩群となってだ。
そうしたこれらの詩語の一言(ひとこと)が、生の充実さへの言葉ともなり、さらには普遍性を連ねた精神へも通底する詩語ともなるのであろう。
そういう詩精神というか、知的感情を内包しているのが詩集『乳粥』の味わいでもあろうか。
なおすでに語ってあることだが、私が再度言っておきたいのは、時間と空間の彼方へ眼を向け、ロマンの香りと歴史の足音をつつんだ詩編は、リアルな心音とともに読む者の心情を捕らえるであろうということだ。
詩人の背負わなければならぬ、《転化精神》の情熱と問う意識を意識を求めつつ--。
朝倉宏哉詩集『乳粥』は、かようなことを伝えてくれる詩心を流露している一冊である。
〈コールサック社/二〇〇六年九月三十日発行/二千百円(税込)